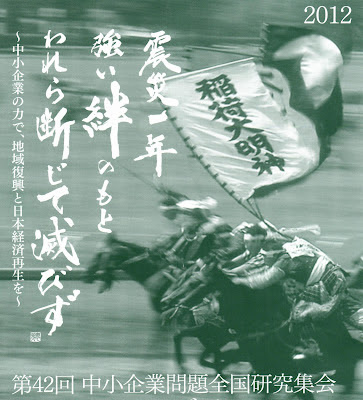〝昔むかし、あるところに、お爺さんとお婆さんが住んでいました。お爺さんは山へ芝刈りに、お婆さんは川へ洗濯に・・・・・〟
日本の昔ばなしの多くは、いつもここから始まりますね。
千年の陶産地である瀬戸も、
「たたら製鉄」の奥出雲も、
陶土や砂鉄が産出するだけでなく、
燃料となる山の木々に恵まれた、といわれます。
いつの間にか、お爺さんは山へ芝刈りにゆかなくなりました。
近頃のお爺さんは、近いうちに、また、行くようになるかも。
エネルギー源は、マラッカ海峡経由でなくても、すぐそこにあるようにも見えます。
(瀬戸市東部、三国山の山頂から)
火曜日, 6月 03, 2014
火曜日, 1月 14, 2014
火曜日, 9月 24, 2013
沈思黙考 而して 乾坤一擲
ヘラジカ(ムース)の武器は、その800キロの巨体と2㍍に及ぶ角。
ヒグマのそれは、同じく巨体と強力な鉤爪
では、人の武器は?
言わずと知れた大脳
考えに考える、自ら考える
沈思黙考 そして 乾坤一擲の行動
土曜日, 7月 06, 2013
来たれ!現代の藤四郎、この瀬戸へ
【1番】
波濤渡り学びし 宋の国は陶の技
帰り来たって 求めるは
想い生かす 陶の土
【2番】
ここは山や川ある 出ずる土は世界一
来たれ藤四郎 住もうぞ瀬戸で
願い生かす このまち
【3番】
ともに暮らそ藤四郎 ともに栄えん陶の地
八百年生きる せともので
想い創る 瀬戸の地
郷土・尾張の国〝瀬戸〟は陶祖加藤藤四郎が活躍した時代から数えて800年。これを記念して〝陶祖八百年祭〟の諸行事を展開中です。わが『瀬戸第九をうたう会』も師走にベートーベンの第九交響曲に併せて新曲〝藤四郎賛歌〟を初演します。その作詞は加藤洪太郎。これを踏まえて地元出身のバイオリンニスト西田博・由美子さんご夫妻が何とオーケストラ仕立てで作曲。
この12月8日、瀬戸市文化センター大ホールでの初演は見のがせません。
瀬戸の地域経済を新生しようと市民サイドでもあちらこちらで有志が集って研究中です。件の作詩者もその幾つかに加わっています。その成果の一つが「陶芸で身を立てようと志す現代の藤四郎を、日本そして世界から瀬戸に招く施策が肝要。核心は人だ」との気づきです。これを賛歌にして〝まち興し〟に参加、です
金曜日, 5月 10, 2013
ヘミングウェイの世界
〝世代をつなぐ〟で我が意を得たり
コヒマル、そこはヘミングウェイの世界。愛艇PILAR(ピラール)号で釣りの日々をおくりながらの著作は〝老人と海〟です。
弟子を連れずに独り海に出た漁師です。その老練な駆け引きで巨大なマグロに釣り針をのみ込ませた。
戦略あやまたず何昼夜もかけた持久の末、遂に舟にたぐり寄せるが、舟より大きく重いため、引き揚げられない。
あの若者とともに来ていれば揚げられるものを・・・・。
港めざして曳航するうち、サメに追われるハメに。次から次へと来襲するサメと挌闘するも、マグロは尾を食われ次第に身を食われ、独りでサメを撃退するには限りが・・・・・。
あの若者とともにきていれば・・・・・。
帰り着いた港で若者が師匠を迎えた時、巨大マグロは頭だけに。
いかに深奥を極めた名人となろうとも、独りの力には限界あり。若者と組んでこそ結果を出せる。
創業45年の弁護士も〝世代を繋ぐ〟陣容あればこその値打ちである。
コヒマルで心密かに「我が意を得たり!」と微笑む。
「創業45年/所員の得意と世代を結ぶ」は、自らの名刺に刷り込んだキャッチフレーズです。
コヒマル、そこはヘミングウェイの世界。愛艇PILAR(ピラール)号で釣りの日々をおくりながらの著作は〝老人と海〟です。
弟子を連れずに独り海に出た漁師です。その老練な駆け引きで巨大なマグロに釣り針をのみ込ませた。
戦略あやまたず何昼夜もかけた持久の末、遂に舟にたぐり寄せるが、舟より大きく重いため、引き揚げられない。
あの若者とともに来ていれば揚げられるものを・・・・。
港めざして曳航するうち、サメに追われるハメに。次から次へと来襲するサメと挌闘するも、マグロは尾を食われ次第に身を食われ、独りでサメを撃退するには限りが・・・・・。
あの若者とともにきていれば・・・・・。
帰り着いた港で若者が師匠を迎えた時、巨大マグロは頭だけに。
いかに深奥を極めた名人となろうとも、独りの力には限界あり。若者と組んでこそ結果を出せる。
創業45年の弁護士も〝世代を繋ぐ〟陣容あればこその値打ちである。
コヒマルで心密かに「我が意を得たり!」と微笑む。
「創業45年/所員の得意と世代を結ぶ」は、自らの名刺に刷り込んだキャッチフレーズです。
日曜日, 3月 03, 2013
中小企業・経営革新等支援機関として活動開始
%E3%80%8D.jpg) コンサルティング
コンサルティング実践セミナー
~~連続3日間の特訓~~
「中小企業経営力強化支援法」(平成24年成立)に基づき「経営革新等支援機関」として認定された税理士や弁護士などの専門職に対する連続3日間の特訓セミナーがありました。
テーマは「中小企業の経営改善計画と事業再生」。
座学とケーススタディーの二本立てで連日9時から17時までたっぷり訓練。
地域金融機関のリレーションシップバンク機能の発揮は、地域経済を支えあうに相応しい中小企業自らの「経営改善計画」の策定と実行が不可欠、というワケである。
その民間に於ける専門的支援者をシッカリと養成し、中小企業憲章がめざす日本経済の復興につなぐ。この基本施策の各論版の一つであることを実感致しました。
中小企業家運動への参画と共に、専門職としてのスキルを時代にふさわしく自らも革新し、以て一隅を照らさんとする覚悟を新たにいたしました。
日曜日, 2月 17, 2013
土曜日, 12月 29, 2012
2013年 ワクの彼方は 青空と陽光
新しい年、2013年に進みました。
一時代を担ってきたこれまでの大型量産産業の役割が海外に移転し、従来の経済・社会の枠組みが通用しなくなってきた様に思われます。
私どもはその前で、日々、活路を求めて試行錯誤の真っ最中。
だが、そのむこうの青き大空には、既に、新しい時代を担う陽光が、小粒ながら鋭く輝きはじめているのに気づきます。
個人の尊厳と人権をより大切にする。
そうした文化に花を咲かせる連帯が、次代を拓く鍵となるとの想いがつのります。
本年も宜しくお願いします。
水曜日, 11月 07, 2012
「経営革新等支援機関」として認定されました
.jpg) 「中小企業経営力強化支援法」(2012年8月30日施行)に基づき、11月5日、全国で2,102機関が「経営革新等支援機関」として認定され、加藤洪太郎弁護士も認定支援機関となりました。因みに、中部経済産業局管内では198機関が認定されております。
「中小企業経営力強化支援法」(2012年8月30日施行)に基づき、11月5日、全国で2,102機関が「経営革新等支援機関」として認定され、加藤洪太郎弁護士も認定支援機関となりました。因みに、中部経済産業局管内では198機関が認定されております。中小企業経営力強化支援法
第十七条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次の業務を行うものとする。
一 経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
制度を紹介する中小企業庁のパンフレットは こちら
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2012/download/1106Nintei_Kikan.pdf
水曜日, 9月 12, 2012
〝もたれ合い〟〝支え合い〟

人と人とが集まってる二つの群れが見える。
見かけは同じように見えても、中身が正反対。
一つは、〝もたれ合い〟集団
「誰かが舵をとってるだろ」と、だれもがお任せで、気楽なもの。
今ひとつは、〝支え合い〟集団
誰も彼も「何のために集まり、力を合わせるのか」を自ら追究して連帯する。
それぞれの行く末は如何?
日曜日, 7月 01, 2012
歴史、そして後世の審判
100年前
この100年
そして100年後
ここは白玉山の山頂。直下に見おろすは旅順口である。1904年暮から1905年正月にかけて、ここで何があったか知らぬ者はない。
賭した目的とそれを実現したうえ辿ったそれからの100年の歴史を振り返る。その目的の設定の意義が歴史的な視野で検証される。
そして今、選択し、行うことの、その結果は、今後の100年の歴史の因果の原因となる。
100年後、再び振り返って検証される。2012年、その選択はどうであったか・・・・・と。
この100年
そして100年後
ここは白玉山の山頂。直下に見おろすは旅順口である。1904年暮から1905年正月にかけて、ここで何があったか知らぬ者はない。
賭した目的とそれを実現したうえ辿ったそれからの100年の歴史を振り返る。その目的の設定の意義が歴史的な視野で検証される。
そして今、選択し、行うことの、その結果は、今後の100年の歴史の因果の原因となる。
100年後、再び振り返って検証される。2012年、その選択はどうであったか・・・・・と。
土曜日, 3月 31, 2012
ひと味もふた味も違う〝まち〟瀬戸
この〝まち〟に来て住んでもよい、この〝まち〟に住みたい、この〝まち〟に住み続けたい。この〝まち〟の産物はいいね。時々行って見たいね。
なぜ?
〝まち〟の真ん中に川があるから。そこに鴨や川鵜そして白鷺がいるから。山が見えるから。陶器やさんや窯元があるから。野の幸、山の幸も結構あるから。
30分も電車に乗れば大都市へも。
そう、ひと味もふた味も違う〝まち〟それが瀬戸
・・・・・第九合唱団ばかりか〝市民オーケストラ〟まであるのです!
瀬戸市民オーケストラは、皆々様の親身のご支援により、定期演奏会も四半世紀の歴史を刻み、今も新たな成長めざして前進中です。今年の定演は2012年6月10日/瀬戸市文化センターでPM2開演です。曲目は、チャイコフスキーの交響曲第5番ホ短調・ハチャトリアンの組曲「仮面舞踏会」・ブラームスの悲劇的序曲。指揮:今村能です。今後とも宜しくお願いします。(写真は、2005年の瀬戸&上海・国際クラシックコンサートでの練習風景)
日曜日, 3月 25, 2012
夜は夜らしく
明かりは、夜の魅力を引き立てるために
 夜を昼に変えようとする煌々たる明かりもあれば、夜をいっそう夜らしく演出する明かりもある。
夜を昼に変えようとする煌々たる明かりもあれば、夜をいっそう夜らしく演出する明かりもある。人とても同じ。
その人がその人らしく生き活躍することを選ぶのか、
はたまた、「普通の人」の如くお仕着せになることを選ぶのか?
夜は夜、昼は昼、夜をわざわざ昼の如くする必要がどこにある?
日曜日, 3月 11, 2012
福島に 全国から1,600名の中小企業経営者が集まり、16の分科会で学びあう
福島の仲間は お元気です
題全国研究集会〟(中小企業家
国協議会主催/設営:福島同友会)のス
ローガンです/1
が全国から福島に集まり再起を誓って学
(写真は、配布されたガイドブックの
表紙から)
をもって転換を遂げて、危機を超える。
他方、緩慢に危機に見舞われる離れた地域で
は、対応も甘くなりがちで、やがて押し
寄せる危機に流されるおそれさえ・・・・・
中国へのビジネス展開をも視野に
今も拡がる
中国の弁護士との実務協力ネットワーク
 クライアントが中国にまでビジネスを展開されることがあっても、そこで遭遇される法律問題にも対処できるようにと、1995年に志をたてました。
クライアントが中国にまでビジネスを展開されることがあっても、そこで遭遇される法律問題にも対処できるようにと、1995年に志をたてました。
以来、国内外に広がるネットワークを確かな基盤として築き続けて今に至り、更に未来に向かって歩みを進めています。
現在までに、全中国15都市の弁護士と協力協定を結んで参りました。
日本側としては、東京・大阪・名古屋の弁護士が4項目の理念によって連携し、〝日中法務交流・協力日本機構〟という社団法人を組織して、プロジェクトを推進しています。
中国の弁護士との実務協力ネットワーク
 クライアントが中国にまでビジネスを展開されることがあっても、そこで遭遇される法律問題にも対処できるようにと、1995年に志をたてました。
クライアントが中国にまでビジネスを展開されることがあっても、そこで遭遇される法律問題にも対処できるようにと、1995年に志をたてました。以来、国内外に広がるネットワークを確かな基盤として築き続けて今に至り、更に未来に向かって歩みを進めています。
現在までに、全中国15都市の弁護士と協力協定を結んで参りました。
日本側としては、東京・大阪・名古屋の弁護士が4項目の理念によって連携し、〝日中法務交流・協力日本機構〟という社団法人を組織して、プロジェクトを推進しています。
グローバルな視野とシフトを実際に備えてこそ、日本における立ち位置を強固にして、地域・社会に貢献できるに違いないと考、そうしたお役に立ちたいと願っているものです。
土曜日, 2月 11, 2012
固定観念を打ち破る/異質を結びあわす閃き
未来を拓くことのできる社会は
これは何?
キリスト教会あるいはイスラム教会の塔堂?
でもよく見れば、彫像のことごとくは天女。そして壁面に居並ぶのは仏様である。
意表をつくとはこのこと。結果を見れば斯くの如しであるが、ヨーロッパの塔堂に仏教芸術をしつらえるなど、破天荒すぎて誰も今まで思いもつかなかった。
未来を拓くことのできる社会は、固定観念を打破し異質を結びあわす閃きと気概ある者をも、大胆に起用するものと知る。
これは何?
キリスト教会あるいはイスラム教会の塔堂?
でもよく見れば、彫像のことごとくは天女。そして壁面に居並ぶのは仏様である。
意表をつくとはこのこと。結果を見れば斯くの如しであるが、ヨーロッパの塔堂に仏教芸術をしつらえるなど、破天荒すぎて誰も今まで思いもつかなかった。
未来を拓くことのできる社会は、固定観念を打破し異質を結びあわす閃きと気概ある者をも、大胆に起用するものと知る。
月曜日, 1月 02, 2012
土曜日, 11月 05, 2011
「不可能」 を 『可能』 にしていく 人と人との協力づくり
杭州市政府の若手職員の心意気
☆ 2011年10月28日と29日の両日、浙江省は杭州で開催中の〝第2回杭州余暇博覧会〟の野外ステージに、わが〝瀬戸第九をうたう会〟はじめ日本全国から集まって編成した日本瀬戸第九合唱団が登場しました。
☆ さて、今回のレポートの焦点は、野外舞台で活躍したグランドピアノ。
 縁あって余暇博覧会に協力することになって、主催者である杭州市政府の担当者と現地で打ち合わせました。そのスタッフの中の人なつこい若者が現場のリーダーとなり、日頃のメールの往復の窓口もつとめるところとなりました。
縁あって余暇博覧会に協力することになって、主催者である杭州市政府の担当者と現地で打ち合わせました。そのスタッフの中の人なつこい若者が現場のリーダーとなり、日頃のメールの往復の窓口もつとめるところとなりました。
☆ 開催日も近くなってのこと。その若者からメールが来信しました。
曰く「グランドピアノは用意できません。演奏会場に車両の乗り入れができず、重量物は到底運び込めないのです。小型のピアノに致します。」
日本から返信メールを送りました。
「了解しました。」
「どんなピアノでも構いません。目的はオーケストラの演奏に代えるピアノ伴奏ですので、一台のピアノを2人掛かりで弾く連弾を可能にすることです。88鍵以上あればよいのです。」
☆ これに対する何の返信メールもなく、当日の本番に至りました。
その朝、事前練習のために会場を訪れると、何と例の若者が指揮して道路からステージまでの2~300メートルの距離をエッサエッサと十数名でグランドピアノを担ぎ歩いて運び込んでいるではないか!
しかも、フルコンサートの大型グランドピアノを!!
演奏会は盛況の裡に成功。「歴史が切り裂いたものを再び結びあわす。全ての人間は兄弟になる・・・・」とのシラーの詩をピアノ連弾の迫力ある伴奏で歌い上げるなかで、日本の合唱団と中国の観衆との間に心が通いあいました。
☆ 下支えする者どうしの相互理解、そして前向きに物事を進めようとする心意気、その上で「不可能」を『可能』にしていく人と人との協力づくり、等々に眼を見張りました。
民間外交の一隅たらんとする文化交流のなかから、明るい将来を確信する出来ごとが生まれたとの想いを深くいたしました。
☆ 2011年10月28日と29日の両日、浙江省は杭州で開催中の〝第2回杭州余暇博覧会〟の野外ステージに、わが〝瀬戸第九をうたう会〟はじめ日本全国から集まって編成した日本瀬戸第九合唱団が登場しました。
☆ さて、今回のレポートの焦点は、野外舞台で活躍したグランドピアノ。
 縁あって余暇博覧会に協力することになって、主催者である杭州市政府の担当者と現地で打ち合わせました。そのスタッフの中の人なつこい若者が現場のリーダーとなり、日頃のメールの往復の窓口もつとめるところとなりました。
縁あって余暇博覧会に協力することになって、主催者である杭州市政府の担当者と現地で打ち合わせました。そのスタッフの中の人なつこい若者が現場のリーダーとなり、日頃のメールの往復の窓口もつとめるところとなりました。☆ 開催日も近くなってのこと。その若者からメールが来信しました。
曰く「グランドピアノは用意できません。演奏会場に車両の乗り入れができず、重量物は到底運び込めないのです。小型のピアノに致します。」
日本から返信メールを送りました。
「了解しました。」
「どんなピアノでも構いません。目的はオーケストラの演奏に代えるピアノ伴奏ですので、一台のピアノを2人掛かりで弾く連弾を可能にすることです。88鍵以上あればよいのです。」
☆ これに対する何の返信メールもなく、当日の本番に至りました。
その朝、事前練習のために会場を訪れると、何と例の若者が指揮して道路からステージまでの2~300メートルの距離をエッサエッサと十数名でグランドピアノを担ぎ歩いて運び込んでいるではないか!
しかも、フルコンサートの大型グランドピアノを!!
演奏会は盛況の裡に成功。「歴史が切り裂いたものを再び結びあわす。全ての人間は兄弟になる・・・・」とのシラーの詩をピアノ連弾の迫力ある伴奏で歌い上げるなかで、日本の合唱団と中国の観衆との間に心が通いあいました。
☆ 下支えする者どうしの相互理解、そして前向きに物事を進めようとする心意気、その上で「不可能」を『可能』にしていく人と人との協力づくり、等々に眼を見張りました。
民間外交の一隅たらんとする文化交流のなかから、明るい将来を確信する出来ごとが生まれたとの想いを深くいたしました。
火曜日, 10月 25, 2011
人間を大切にする社会への扉をこじ開ける
 ラベルライターに関する発明をしたブラザーの社員と元社員とが、社員発明の貢献による適正な対価の支払いを会社からうけるべきであるとして、地裁から高裁へ、そして最高裁で頑張ってきました。
ラベルライターに関する発明をしたブラザーの社員と元社員とが、社員発明の貢献による適正な対価の支払いを会社からうけるべきであるとして、地裁から高裁へ、そして最高裁で頑張ってきました。東京高裁は東京地裁が命じた支払額の五割増しの支払いを命じましたが、この高裁判決がこのほど最高裁判所で確定するに至りました。
新聞報道によれば会社側は「決定内容は残念だが最高裁決定には従いたい」とコメント。
この裁判、相談役を求められて戦略方面など支援しましたが、主力は当事務所の夏目武志弁護士と事務局の佐々木と松田の三名。得意めざす分野のひとつとして知財分野を選択して陶冶に努めていた夏目が、本人の酒井さん結城さんと文字通り三人四脚でここまで頑張り抜きました。
「大量生産基地」が海外移転を余儀なくするなか、国内ではその「開発基地」たる役目を担って雇用を確保する、これが我が国の活路のひとつであることは、今では、はっきりしてきています。
開発のひらめきやヒント、そして新たな工夫は、他でもない人間の考える力から生み出される。新興諸国に先行する開発は、先進国に相応しい〝より人間らしい生活〟であればこそ益々生まれる。
個人として尊重される「個人」どうしが対等に協力しあってこそ、真のチームワークの力が発揮されよう。
獅子をも飼い慣らす智恵、すなわち大脳をもつ本来の人間を大切にする社会への扉をこじ開ける裁判となりました。
何ごとも人組(ひとぐみ)から/京都『時代祭』をお手本に
秋の京都〝時代祭〟のことです。
午前中から平安神宮の境内のあちこちに刀や槍を手にした胴丸姿の足軽隊、本格的な鎧兜の武将、堂々の体躯の牛が曳く御所車、お公家さんやお姫様、たくさんの馬などなどが参集し始め、次第に活気が満ちはじめました。十時頃になると、順次、丸太町通を西に進んでスタート場所の京都御苑への移動が始まりました。
御苑に終結して待機するうち、正午となる。本番である。最先頭部に行列の名誉奉行の馬車二両が出る。一両目には京都の府・市各議会の議長さんが座乗され、次いで副知事さんや市長さんが座乗される二両目が続きます。
で、この馬車の御者は誰?どこかで見た姿かたちでは??
御苑の広々とした砂利道を行列は進みはじめる。烏丸通を南下して東に折れると、両側の特設桟敷の内外が見物の人々で埋まる御池通である。真ん中を馬蹄も軽やかに進む。姿勢を正して御者台からみる京都はことのほか爽やか。思わず空を仰ぐ。河原町通そして三条大橋をわたる頃には道幅も狭くなり沿道の人々と馬車上のやんごとなき方々とが互いに声を掛け合うと、御者までがニッコリとしてしまいました。ラストは、神宮通を次第に迫る正面の大鳥居を見て北上し平安神宮に帰り着いて、互いにお役目ご苦労様となりました。
さて、この時代祭の行列、例の鼓笛と共に進む維新の官軍に始まり、歴史を順に辿って藤原そして延暦時代にまで遡る一大絵巻である。各時代を象徴するそれぞれの行列は、これを京都の市民の皆さんが学区単位で組織をつくって編成。練習に練習を重ねて出場を受け持ちあっておられるというからすごいと思いました。時代考証に忠実な衣装・装具を再現する伝統技術を保存し成り立たせる、その資金創りも一大運動となるようです。
京都三大祭りの〆、秋の時代祭はこうして催される。
舞台裏の一端から参加させていただき、京都の真の強みはこの住民力であることに気付きました。わが郷土のまちおこしも、実は、市民の人おこしであるべきことを、そして何ごともそのベースが〝人組〟にあることを、お手本に触れて学ぶ秋の一日となりました。
登録:
投稿 (Atom)